おはようございます。
こども食堂【虎吉】店主・高木のひとりごとです。
本日のテーマは『こどもが友達と遊ばないのは友達がいないから?友達を作れるかどうかは親にかかっている』。
子育てをしてると、ふと我が子の友達関係の事が気になったりする。
うちの子は友達がいるのかしら…
ずっとひとりで家に居るけど大丈夫かしら…
大丈夫。
今現在友達がいないと感じてても、それは何の問題もないこと。
大切なのは本人がどう感じてるか、ということ。
いらぬ心配をしてるだけかもしれないし、もしかしたら親に原因がある可能性もある。
親が見過ごしてることとか、もしかしたら見て見ぬふりをしてることがあるかもしれない。
いろんな観点から考えないと、痛い目に合うのは「こども」であり、それが親にふりかかってくることもある。
本人の性格を考える
まず本人がどう考えてるのかを知ることが大切。
友達がいないことを悩んでいるのか。
別にそんなことはどうでもいいと思ってるのか。
本人が悩んでるなら、その原因が何なのかを探ったり、いろいろ考えてあげないといけないけど、大抵の場合は親の杞憂にすぎない。
過保護にし過ぎている、という可能性もあるので、こどもをしっかりみて何を考えてるのか、どんな性格なのか、をちゃんと把握することが大事。
悩んでるけど言い出せない…なんてこともあるかもしれない。
それは本人にしかわからないこと。
もしかしたら、友達と遊ぶことよりもひとりで遊ぶことの方が楽しい、ということもある。
マイペースなこどもはそうなりがち。
僕自身そんな時期があって、友達と遊ぶことよりもひとりで絵を描いたり、工作をしてる方が楽しかった。
他の子たちが習い事をしていて遊べない、なんてことも考えられる。
そういうことは、聞かないとわからない。
こどもにしれっと聞くのもアリだし、親同士で話したりして情報収集する、という手もある。
何にせよ、こども本人が何を考えてるかとか、何が好きかっていうのをキチンと把握することが親としてできること。
友達がいない原因が「親」である可能性
仮に友達がいないのだとしたら、その理由を明確にしないといけない。
いろんな可能性がある。
ひとつは本人の性格とか資質の可能性。
これはひとりで遊ぶのが好きだとか、まわりの子たちと遊んでても面白くない、とかそういったもの。
これはもうどうしようもない。
無理やり友達を作らそうとしても、ストレスにしかならないので温かく見守っていればいい。
友達がいない理由が「親」である可能性もある。
これは僕自身がそうだったんだけども。
物心ついた時から親に対して心を閉ざしてしまって、他人と関わることがすこぶるニガテで、他人に心を開くことができなかった。
がんばって友達ができたとしても、本音をなかなか言うことができず、「何を考えてるかわからない」と言われた。
常に他人の顔色を窺って、去るもの追わずの精神も手伝って、誰も居なくなってしまった。
これは自分ではなかなか気づけないことで、僕自身そのことにようやく気づけたのは40歳を過ぎたあたり。
そんな人間もいるんだす。
ほとんどのこどもは親からの無条件の愛情を通して安心感を得ることができる。
それを積み重ねることで、いろんな人と心を通わすための土台を形成する。
これを愛着の土台というらしく、僕みたいに安心感を得られなかった人のことを「愛着障害」なんていったりする。
親に対して心を閉ざした原因は、僕が毎日オネショをしてしまってて、親に怒られたこと。
オネショは膀胱が未発達だったり、眠りが深くて尿意で目覚めないことだったり、精神的なものが原因。
僕の場合はどれだったのかわからないけど、どのみち、自分でコントロールしてどうこうできるものじゃない。
それを理不尽に怒られることが積み重なって、親に対して不信感しかなくなった。
こどもにとって「親に愛されてる」ということを実感するのは非常に大切なこと。
その実感があるからこそ、それを土台にして甘えたりワガママを言ったり反抗したりできる精神が身に着く。
それができないのは親が理不尽にこどもを怒ったり感情的になって暴力を振るったりする虐待とか、親が不在だったり不仲だったり、過干渉になったりとか、いろんな要因がある。
親と子のコミュニケーションがうまくいってないと、対人関係に支障が出ることがある。
小さいこどもにとって親は唯一の心の拠り所であるということを自覚しないといけない。
友達という言葉の捉え方
そもそも。
ひと口に「友達」と言っても、いろんな友達がある。
大人でも、どこからどこまでが友達なのか。そこの線引きは難しい。
一緒に飲みに行けば友達として成立するのか。
趣味が合えば友達なのか。
仕事仲間は友達と言っていいのか。
などなど。
人によってその捉え方はさまざま。
結婚とか交際はどちらかが宣言して、相手がそれを承認すれば関係は成り立つ。
だけど、こと「友達」においてはその境界線がない。
まして、小さいこどもならなおさら。
「友達になって」ってどっちかが宣言して関係が始まるわけでもないし、いつの間にか一緒にいることが多くて、よく考えたらアイツは友達なのかなぁ?ぐらいの非常に曖昧なもの。
友達かどうかよりも、「その人と一緒にいたら楽しい」とか、立場とか権力とかそういう損得抜きで、対等にお互いを尊重し合えるような関係が理想なのではないかな、と。
相手が困ってたら自然と助けたいと思えたり。
自分が困ったら助けてって言えたり。
お互いの悪い所はちゃんと言い合えたり。
そんな関係が「友達」なんじゃないかな。
そんなふうに考えると、僕は今までホントの意味での友達はいなかった。
どっちかって言うと、友達っぽい人に依存してただけ。
ひとりになるのが怖かった。
だから誰かと一緒にいることが増えたとしても、いつも聞き役に回って、その人が前向きに考えれるようになるにはどうしたらいいだろう?っていうことばっかり考えてた。
それは「自分の本音を言ってしまうとその人が離れていってしまうかもしれない」という恐怖が常にあったからだった。
友達がいる=幸せとは限らない
友達がいれば幸せなのだろうか?
必ずしもそうとは限らない。
親の前とかでは「友達」のように振舞ってても、実は陰で陰湿なイジメに遭ってたりすることもある。
それが親にはわからないように口止めされてたりすると、発見のしようがない。
気づいた時にはもうずいぶん精神が崩壊してたり、自ら命を絶つなんてことにもなりかねない。
そんな見せかけだけの友達ならいない方がマシだ。
大事なのは、その友達がお互いを尊重し合える関係かどうか。
でもそれは本人同士にしかわからないこと。
なので親は我が子のよく一緒にいる子との関係がうまくいってるかどうかをちゃんと見極めないといけない。
温かく見守っていればそのうち友達はできる
友達を作って人間関係を築いていくことは、コミュニケーション能力が磨かれるので、社会を生きていく上でとても役に立つこと。
世の中では友達がいることが当たり前っていう風潮もある。
だから親はこどもに友達ができたかどうかが心配になるし、学校の先生も同じように友達を作ることをすすめる。
今現在、一緒に遊ぶ友達がいなかったとしても、温かく見守っていればそのうち気が合う人が現れる。
大切なのは本人がどう感じてるかを把握すること。
親はあまり過干渉にならず、なんでも話してくれるようにドンと構えておくこと。
それがいちばん難しいことではあるけど、それが親の役目。
友達関係は大人にとっても非常に難しい問題。
まずは大人がちゃんと自分を見つめ直すことが大事なのかもしれない。
ご清聴ありがとうございました。


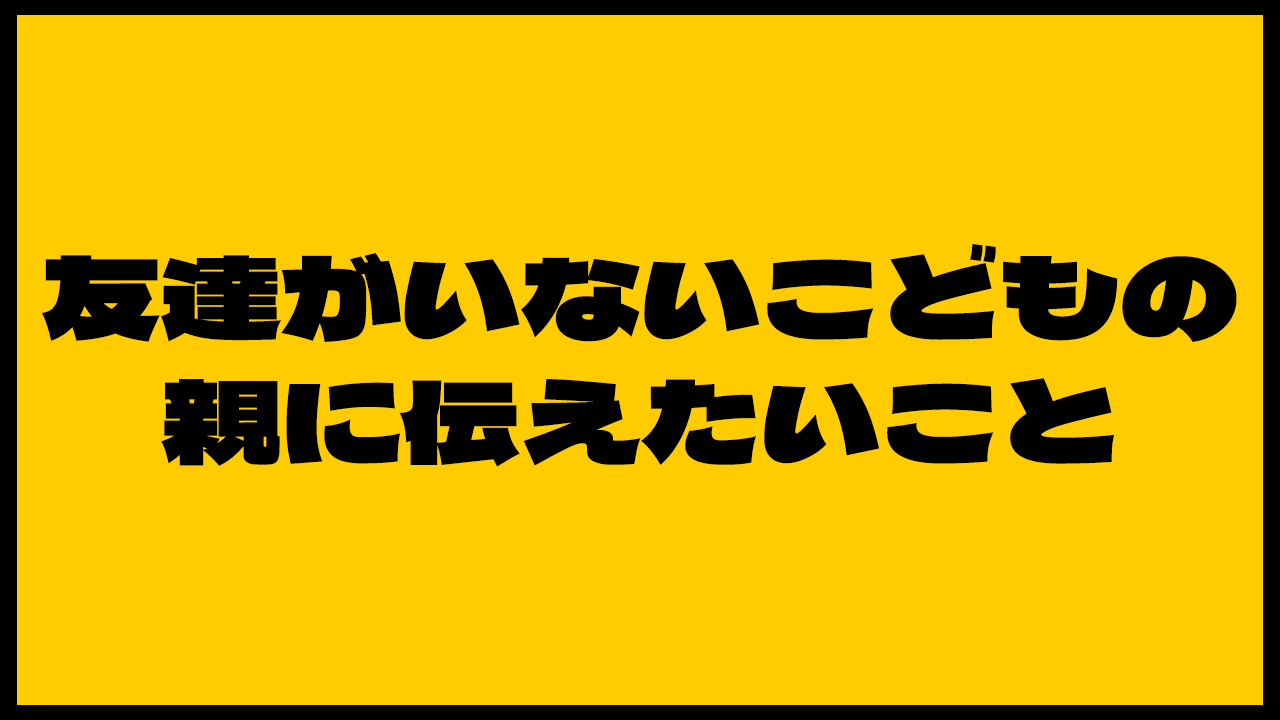


コメント