おはようございます。
こども食堂【虎吉】店主・高木のひとりごとです。
本日のテーマは『こどもが話してくれないのは受け入れ体制ができていないから』。
どっかで「こどもが話をしてくれない」という記事をみて、はてさて自分はどうなんだろう?と考えてみた。
#どこかは忘れた
#スマホをいじってたらふと出てきたものをピャッと
僕はというと、自分のこどもはもちろんのこと、こども食堂にやってくる子たちも自分からたくさん話をしてくれる。
僕が特に何かを話しかけるわけでもなく。
勝手にペラペラペラペラと。(笑)
全員が全員というわけではないけど、8割〜9割ぐらいの子はそんな感じ。
なので「話してくれない」なんてことがあるんだ、と不思議な感覚になった。
その記事をみてて感じたのは親がこどものことをちゃんとみていないなぁっていうこと。
もっと言うと、「こどもだから」と完全に舐め腐って、モノのように扱ってるなーというのが全体的な感想。
え?
こどもってひとりの人間じゃなかったっけ?
なんでそんな自分のモノのように考えてるの?
そういう親が多いんだとさ。
でもこれはあくまでその記事の中での話。実際にはそんな親ばっかりじゃないことは知ってる。
でもそれが記事になるってことはそれだけ需要があるってことで、世の中には少なからずそんな悩みを持つ親御さんが一定数いるということ。
ふーん。
そもそも。
話してくれないって言ってる時点で自分のことしか頭にないよねって思う。
メンヘラかよ。
自分はちゃんとこどものことをみてますよ、ってどこぞの知らない誰かに認めてもらいたいとか、こどもを自分の支配下に置いときたいっていう自分中心の感情がすけてみえる。
こどもだってひとりの人間で、人格もあるし意志もある。
でも、話してくれないって言ってる親たちの脳みそにはそんな考えはないんだろう。
そしてこどもは大人よりも感受性が豊かだからそういうのは敏感に感じ取ってしまう。
そんな自分のことしか考えてない人間と話したいなんて思わない。
だから「話してくれない」んだよ。
話してくれないじゃないんだよ。
同じ「人」なんだ。
ひとりの人間として対峙しないと一生壁ができたまんまだ。
「話してくれない」を解決するいちばんの近道はまずココかな。
その上で。
自分からいろいろ話をしてくれるようになるには、こどもが「自分を理解してくれてる」っていう安心感を作ることが大切。
それがあれば勝手にペラペラペラペラしゃべってくれるようになる。
じゃあその「安心感」を作るにはどうするか?
これは非常にカンタン。
こどもに「え?なんでわかったん?」って言わせる。
それを何回も繰り返す。
それだけ。
そうすれば少しずつ「自分のことを理解してくれてる」っていう信頼が積み重なっていく。
これが難しいと感じるのは、こどものことをよくみていない証拠。
こどもに限ったことじゃなく、人には行動とか言動のクセというものがある。
そのクセはよく観察してればみえてくる。
クセを理解して行動を先読みして「コレ」でしょ?を提示する。
そしたら「なんでわかったん???」って目ん玉ひんむいて驚いてくれる。
たとえば。
今ドラえもんをみながらコレを書いてるのでのび太くんの行動パターンのクセを読み取ってみよう。
のび太くんなら日本国民誰もが行動パターンを知ってるはずっっ。
まず。
のび太くんは昼寝が大好き。
しずかちゃんが大好き。
射的が天才的。
あやとりも天才的。
ママは苦手。
でもママのことは大好き。
勉強も苦手。
運動も苦手。
スケベ。
授業中に寝て先生に怒られて廊下に立っとれー。
だいたいこんな感じ。
もうひとつ大切なことは、底抜けに優しいこと。
自分が寝そべってた場所にタンポポの花が咲いていたのを知らなくて潰してしまった。
それを「ゴメンよ」と言いながら添え木をつけて元に戻してあげたり、どんな異形の宇宙人とか、手のひらサイズの小人とかでも分け隔てなく接することができる。
そんな底抜けの優しさを持ってるのが彼の素晴らしいところ。
これが誰もが知ってるのび太くんのおおよその人間性。他にもたくさんあるけど、とりあえずこれぐらい。
まず大前提としてこれぐらいの情報を持つことが大切。
さて。
のび太くんの目ん玉をひんむかすにはどうすればいいか?
まず誰の立場で考えるか。
いちばん身近で驚きを与えるのにうってつけの人物はママだ。
ママはほぼのび太くんを叱ってばかりなので驚きを与えるにはちょうどいい。
ドラえもんも叱ってるけど、同じぐらい甘やかしてもいるので驚きを与えるまではいかない。
のび太くんが学校から帰ってママがまずいうことは「宿題は?」。
これはのび太くんがいつも宿題を忘れて先生に叱られるという行動のパターンがあるからだ。
宿題を忘れるのはのび太くんは勉強が苦手だから。
学校で出された宿題があやとりだったら彼は喜んで宿題を優先させるに違いない。
でも現実はそうじゃない。
だからこそママはのび太くんが先生に叱られないように「宿題は?」と聞く。
それはのび太くんのためでもあるけど、ママ自身が先生に何も言われたくないっていうのもあるのかもしれない。
じゃあどうやったらのび太くんを驚かせられるか?
ここではママの「先生に何も言われたくない」っていう保守的な考えはとりあえずフル無視して、のび太くんを驚かすという一点のみにフォーカスして考えてみる。
のび太くんはまず何をおいても「昼寝」だ。
なので昼寝用に布団を用意しといてあげると驚いてくれるんじゃないかな。
「どうしたの?ママ」なんつって。
それだとあまりにも不自然で逆に気持ち悪がられる可能性もあるけど。笑
でも驚きを与えるにはそれぐらいのことをした方がいい。
で、昼寝を終えたら次はあやとりを教えてもらおう。
それこそ昼寝よりも「ママどうしたの?」ってなるかもだけど。笑
それこそが目ん玉をひんむくぐらいの驚きを与えるということ。
でも最初はそうかもしれないけど、それを毎日継続してやったらどうなるだろう?
のび太くんも最初はビックリして疑心暗鬼にしかならないだろうけど、毎日継続してやっていれば少しずつママに心を開いてくれるんじゃないだろうか?
のび太くんからママにたくさん話しかける未来がちょっとはみえたんじゃないだろうか?
「今日のあやとりは何を作る~?」なんつって。
こればっかりはやってみないとわからないけど、可能性はじゅうぶんにある。
ダメだったらまた違う方法を考えればいい。
のび太くんは架空の人物だし、直接話したことも空気感を共にしたこともないからわからないことがたくさんあるけど、現実にやるのは血の通ったひとりの人間だ。
自分のこどものことはいちばん近い存在である親がいちばんよく知ってるはず。
何が好きか。
何が苦手か。
それと行動のクセやパターンを見抜いて先読みして目ん玉をひんむかすぐらいの驚きを毎日継続して与えていれば、安心感を生むことができて、自ずと「話してくれる」ようになる。
ご清聴ありがとうございました。


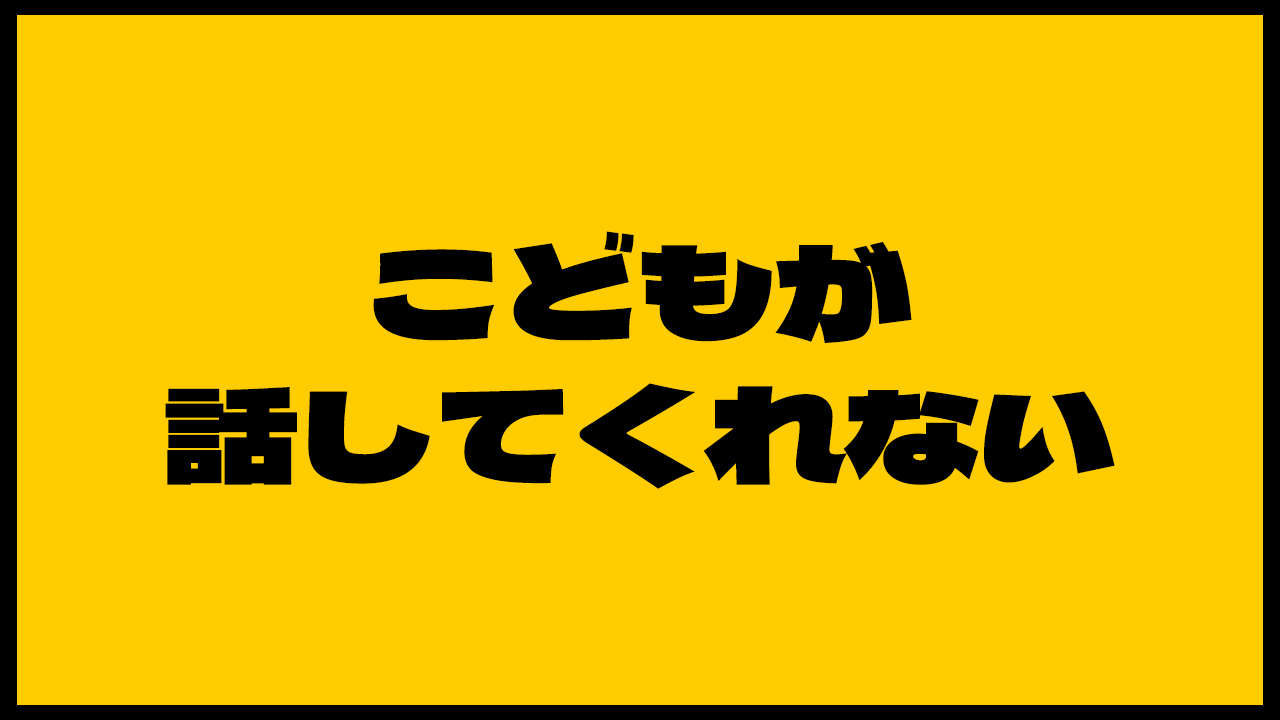
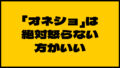

コメント