おはようございます。
こども食堂【虎吉】店主・高木のひとりごとです。
本日のテーマは『お墓参り』。
虎吉まわりはお盆で人がいない。笑
虎吉はお盆もお正月も通常営業。
お休みは気分次第。
オープンしてからほとんど休むことなく営業してたらお客さんに「たまには休みーや」って言われる始末。
最近は適度にお休みいたしてござる。
お盆休みの最中はお店まわりも人の気配が普段よりも薄く、すごくのんびりした一日になる。
…つってもまだ2年目で、去年はオープン直後だったからまだまだ全然塩梅がわかってないんだけども。
僕も虎吉の前の仕事ではお盆休みがあって、実家に帰ったりしてた。
その時にじいちゃんのお墓参りをしたりしなかったり。
そんなお墓参りについてふと考えた。
お墓参りはお彼岸とお盆の2種類。
一般的にはお盆は8月13日〜16日の間にお墓参りをする人が多い。
8月13日が迎え盆で16日が送り盆。
お彼岸は春分の日と秋分の日の前後3日を含んだ合計7日間。
令和7年なら3月17日が春彼岸入りで20日の春分の日が中日、23日が春彼岸明け。
9月20日が秋彼岸入りで23日の秋分の日が中日、26日が秋彼岸明け。
なんだそう。
その期間にお墓参りをしてご先祖さまを供養して感謝を伝えるのがお墓参りの礼儀作法。
これは日本で古くから伝わる風習で、仏教の教えからきてるんだとか。
とはいえ。
必ずお盆とかお彼岸の時にお墓参りをしないといけないという決まりはない。
てゆーか。
そもそも仏教自体、そんなに日本で浸透してるわけでもないし、昔に比べたらはるかにそういうものに対しての信仰心は薄れてる。
無宗教っていう人も多いし、昔からそうやってるから「ただなんとなく」そうしてる人もたくさんいる。
僕もそのひとり。
無宗教だし、昔からそうやってるっていう「伝統」があるからなんとなくそうしてた。
とはいっても、お墓に行ってタバコに火をつけてそれを線香刺すところに刺して手を合わせて終わり、っていう礼儀作法もクソもないもの。
お墓を掃除したりお花を持ってきたりとかは一切していない。
たぶんマナーとかにうるさい人からしたら「なんてことを……💢」と思われるようなことをしてる。笑
でも僕はそれでいいと思ってる。
なんならお墓参りなんてしなくてもいつでも故人を偲ぶことはできる。
しょせん仏教の通例行事のひとつ。
仏教の開祖のお釈迦さまは手塚治虫氏の「ブッダ」でその生涯が描かれてて、読んでとても感動したのを覚えてる。
こんな人が過去に実在したのか、と。
でもお釈迦さまだってひとりの人間。
マンガを読む限り、その時代では考えられないぐらい優しい人だ。
彼が現状の仏教を信仰してる人たちをみたらどう思うんだろう?とか考えたら、あんまりいい顔をしないんじゃないかなーとか思ったりする。
まぁご本人もうとっくになくなってらっしゃるし、真相なんか確認のしようがないけど、少なくとも僕はそう思う。
故人に対して気持ちがあればいいので、写真をみて感傷に浸ることだけでも偲ぶことになる。
命日に故人を思い出すだけでも偲ぶ行為のひとつだし。
故人を偲ぶのにもいろんなやり方がある。
命日というワードで思い出したけど、葬式だってお通夜だってそもそも仏教の儀式じゃん。
仏教の開祖のお釈迦さまはネパールあたりで生まれた人なのになぜ日本には仏教が浸透してるんだろう。
ってことで気になったから調べてみたら、仏教が日本に伝わったのは6世紀ぐらい。
およそ1500年も昔の話。
Wikipedia先生によると、人物としてのお釈迦さまは「仏教というものを説かなかった」らしい。
お釈迦さまが説いたのはいかなる思想家・宗教家でも歩むべき真実の道なんだ、っていう哲学的なこと。
それを後世の経典作者が仏教という特殊な教えを作ってしまったのだ、と。
ほえー。
じゃあなおさら僕のさっきの考えが真実に近いのかもしれない。
とすると、お墓参りだとかお葬式だとかそんな儀式めいたことは誰かが得するために始めたこと、と言ってもいいのかもしれない。
そんなものが風習になってしまったニッポン。
まぁそれを今さらどうこう言ったところで何も変わりはしないし、僕の中での真実があればそれでいい。
お彼岸とかお盆とかそういうものに対してずっとあった違和感。
それはお釈迦さまの説いたものと伝統と言われるものにまでなった儀式めいたものがまったくの別モノだったってこと。
それを知ってしまったらなおさらお彼岸とかお盆にお墓参りに行く意味がなくなってしまった。
行きたいと思った時に行こう。
なんならばあちゃんが亡くなった時、葬式に参加しなかったのも、そういうのが薄々感じ取れていたからだ。
葬式には参加しなかったけど、ばあちゃんの棺の顔だけは見に行った。
それだけでじゅうぶんだと自分で判断したからだ。
まわりの人たちはビックリしてたけど。
そんな感じでもいいんじゃないかな?
社会人としてはどうかとも思うけど。
こういう人間がいたっていい。
ご清聴ありがとうございました。


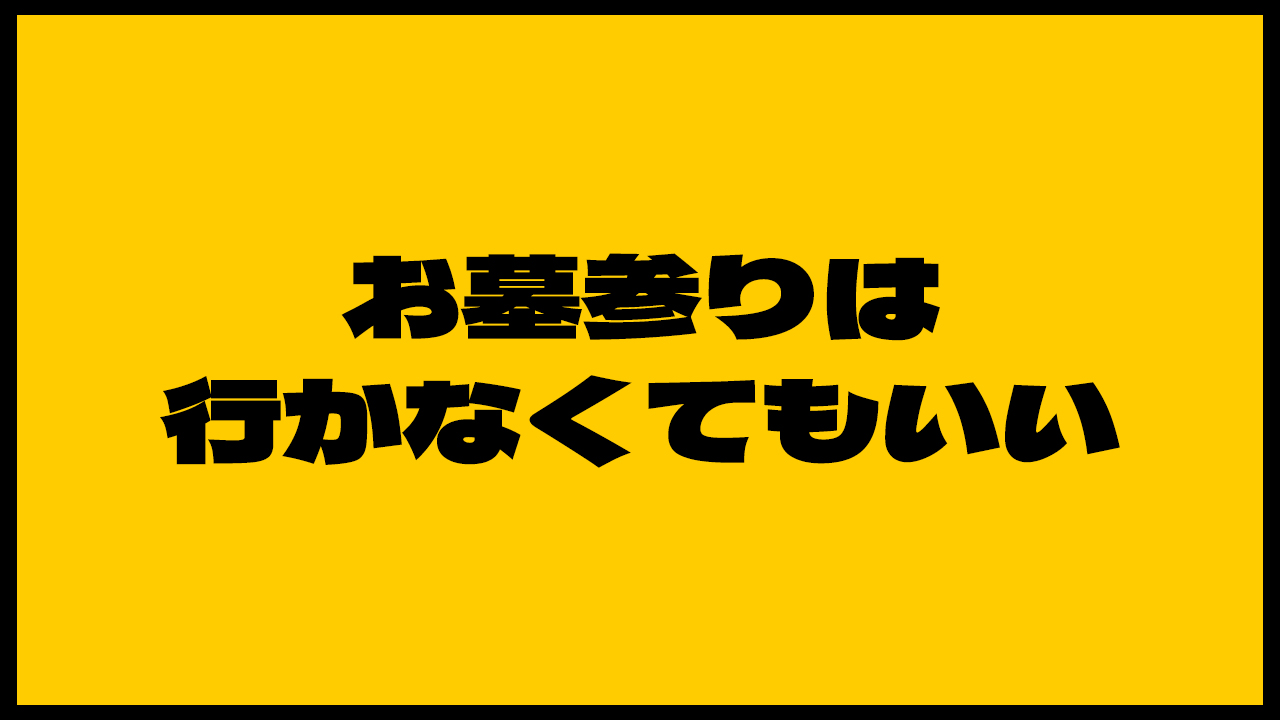


コメント