おはようございます。
こども食堂【虎吉】店主・高木のひとりごとです。
本日のテーマは『音楽にジャンル分けなんていらない』。
音楽にはいろんなジャンルがある。
ロック、ブルース、ジャズ、ファンク、テクノ、ヒップホップ、ソウル、R&B、クラシック、レゲエ、などなど。
細かく分けていくともっといろんなものがある。
だけど、中にはこれは一体何に分類されるんだろう?っていうのもたくさんある。
全体的にロックっぽいんだけどなんかジャズの要素も入ってる、みたいなのとか。
Aメロ、Bメロはファンクでサビで急にテクノになったりとか。
言い出したらキリがないぐらい。
ジャンルという垣根を飛び越えて新たな音楽がたくさん生み出されてる。
じゃあもう別にジャンルで分ける必要なくね?笑
音楽は自由だ。
って思うんだけど、今あるものをなくそうとしたところでそんなのムリな話。
さて。どうしよう?
いろんな表現方法があって、それが世界中どこでも共有できる時代になった。
そういう傾向は僕が音楽を真剣に聴き始めた中学生の時からすでにあった。
CDやレコードは世界中に流通されてるし、ラジオやテレビでもいろんな音楽を聴くことができたから、それによっていろんな音楽を取り入れることができたからだろう。
それが今ではインターネットですぐに聴きたい音楽を検索できる。
なんならスマホさえあれば5秒もかからずに好きな音楽が聴けるようになった。
しかもイヤホンとかヘッドホンを装着すればすごく高音質で。
だからこそ、音楽のジャンルの垣根がほぼないと言っても過言ではないぐらい、いろんな音楽の融合があちらこちらで起きてる。
作り手側からするとこんなにも面白いことはない。
曲作りで行き詰まった時とか、こんな音が欲しいなーって思った時にすぐにいろんな音が聴ける。
むしろいろんな音がありすぎて選択肢に困るぐらいだ。
僕は基本的にはいろんな音楽を混ぜて新しいものを作りたい人間なんだけれど、ジャンルにこだわる人もたくさんいる。
ロックはこうだ!
とか
これがジャズだ!
みたいな。
それはそれでべつにいいとは思うけど、もうちょっと柔軟に考えた方が面白いんじゃないかなーと個人的には思う。
そもそもロックだってもとはといえばブルースとかカントリーを基に進化していった、いわば融合されたダンス音楽だ。
その音楽に反体制的なメッセージとか社会的なテーマの歌詞をのせて歌うのがロックンロールの定義とされてる。
「ロック」というひとつのジャンルの中でもさらに枝分かれして、いろんなロックがある。
ジャズも同じくブルースが基になってるから、そういう議論って何のためにするんだろう?っていつも不思議に思ってた。
人それぞれ捉え方って全然違うし、そのこだわりのせいでバンドの雰囲気が悪くなる、なんてこともある。
そういうのをみてると音楽のジャンル分けなんかいらんよなー、って思う。
作り手側はそういうところにこだわる人は多いけど、聴き手側でもそういうことがある。
聴いてもいないのにジャンルの名前を聴くだけで毛嫌いするような人だ。
アコースティック(生音)音楽が好きな人が電子音楽を嫌う、みたいな。
生音、生楽器のロックンロールは好きだけど電子音楽のテクノは嫌い、みたいな。
逆もしかり。
いや、聴いてからにして?笑
そういう事象があちらこちらで起きてる。
ほんでいざ聴いてみたら「思ったよりいいやん!」みたいなことほざきやがる。
だから言ったじゃん……
もう…二度手間じゃん……
聴く側にとってはあんまりメリットがないんじゃないかと思うこのジャンル分け。
作り手側にとっては便利なところもある。
今の時代は特に。
ひとりで作ってる時、たとえばボサノヴァのリズムが欲しくてそれが頭の中でどんな音だったか再生できない時がある。
そんな時に、パソコンで検索すればいろんなボサノヴァ音楽がヒットするからそれを聴いてその詳細を知ることができる。
他のあらゆるジャンルでもそれが可能で、細分化されていればより作業効率はよくなる。
これはジャンル分けというものが確立されてるからこそできることで、すごく便利。
さらに他の人と共作する時にもジャンル分けはすごく便利。
たとえば「ここの間奏はジャズみたいな雰囲気でお願い」っていう注文をつける時なんかはジャンル分けされてるからこそ、曲のイメージの共有が素早くできる。
もしジャンル分けという概念がなかったら、その曲のイメージとか雰囲気を伝えるのにすごく苦労する。
しかも大まかなジャンルだけを伝えることで、相手に大部分を委ねることができる。
たとえば「ジャズ」とだけ伝えると、その人なりのジャズのイメージでアレンジしてくれる。
自分の中にはなかった新しいアプローチをしてくれることがあるので、それはすごく刺激になるし、新たな扉が開かれるみたいで面白い。
逆もしかりなんだけど。。。
作業効率を上げるのにジャンル分けはあった方が便利。
人それぞれジャンルの捉え方って違ったりするから、そこは実際に演奏してみてから微調整が必要な時もあるけど、何も無いよりかは全然違う。
そう考えるとジャンル分けいらない説があやふやになってきた。笑
まー人間はカテゴライズしたい生き物だし。
地球が丸くて広い世界である以上、どうしても地域によって文化の違いとか言葉の違いとかが生まれる。
その地域によって奏でられる音にも違いは出てくる。
それを止めることはどうにもこうにも不可能だし、すでにあるものをひとくくりにすることもできない。
そしてそれを扱うとなると、どうしても名前があった方がいろいろ効率はいい。
大事なのは今あるものをどうしていくか。
今あるものを融合して聴いたことないような音楽を作るのもいい。
でも今ある音楽でも、それはそれで今の時代を生きる人が演ると今の音楽になる。
その人にしか出せない味になる。
やっぱ音楽っておもしれー。
ご清聴ありがとうございました。


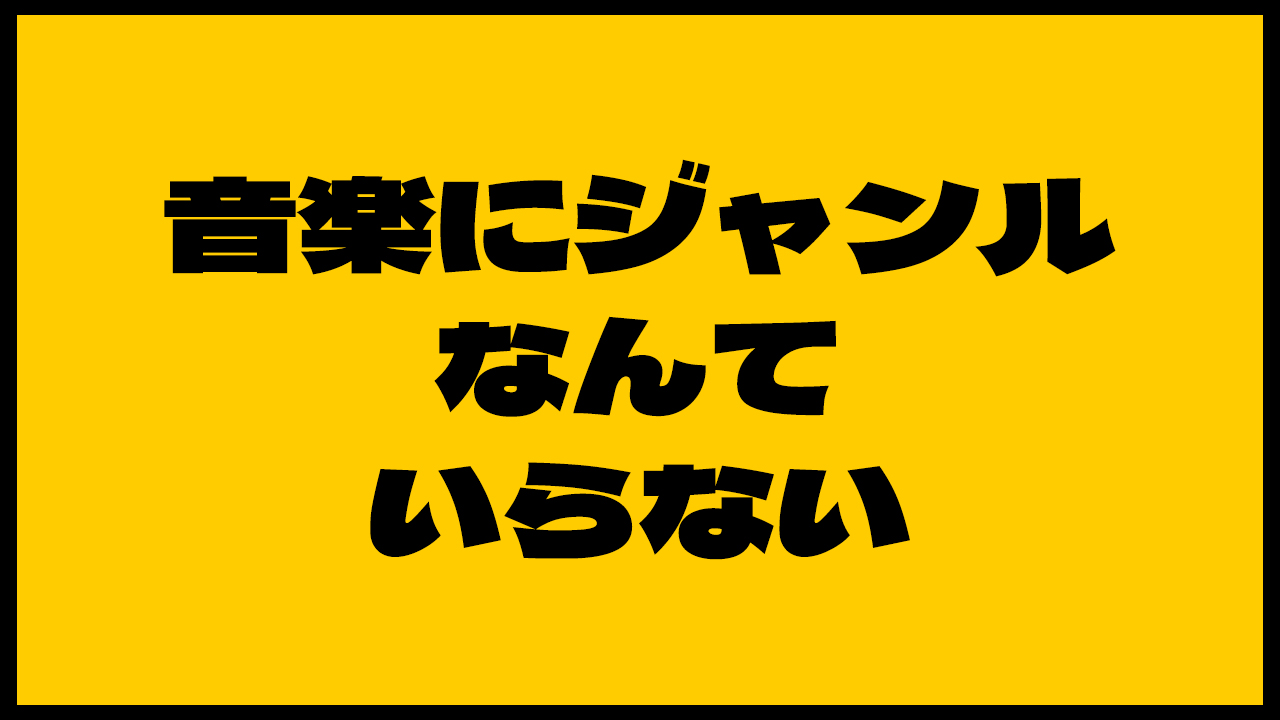


コメント