おはようございます。
こども食堂【虎吉】店主・高木のひとりごとです。
本日のテーマは『思春期のこどもの取り扱い説明書』。
思春期のこどもは口を聞いてくれないとか、思春期=反抗期みたいな感じで難しいお年頃。
付き合い方を間違えると反抗期に突入したりして親子関係が崩壊してしまうこともある危険な時期。
思春期のこどもと仲良く過ごすための取り扱い説明書でござる。
思春期って何?
そもそも思春期って何なんだ?と。
思春期は文字通り「青春期」を「思い始める」時期。
まぁ、、♡
ロマンチックだこと。
身体的にも精神的にもこどもから大人に変わろうとする時期で、昆虫でいうと幼虫から成虫に変化する途中の「サナギ」みたいなもの。
年齢でいうとだいたい11歳ぐらいから20歳ぐらいまでっていうのが一般的。
個人差がすごくあって、15歳で終わったり18歳で終わったりするからまったく読めない。
人によっては思春期なんかなかったって人もいらっしゃる。
もっと踏み込んだ豆知識。
11〜14歳を思春期、それ以降を青年期と呼ぶ。
11〜20歳の全体を「青年期」と呼ぶこともある。
青年期の初期が11〜14歳で、中期が14〜17歳、後期が17〜20歳と分けることもある。
でも一般的にはだいたい思春期=中学生っていうイメージで、青年期なんて言葉があること自体知ってる人は少ないっぽい。
思春期は身体的、精神的にいろんな変化が起きる。
その変化にどう向き合うかが大切。
ほとんどの人ができてないこどもとの向き合い方
思春期に突入すると、性ホルモンの分泌が上昇して肉体的な変化が起きる。
女子は乳房がふくらみ始めて、月経が始まって、カラダも丸みを帯びて「女子」から「女性」へと成長していく。
男子もヒゲが生えたり声変わりが起きたり、カラダがゴツゴツ筋肉質になったりして「男子」から「男性」へと成長していく。
小学校の頃を知ってる子で、中学生時代を知らなくて、高校生になって久しぶりに会ったら「ダレ???」って聴きたくなるぐらい見た目が変わってることがザラにある。
それぐらい成長を遂げる時期で、思春期に突入したこどもはいろんな身体の変化が起きたりしてその影響で情緒不安定になったりする。
異性を意識し始めたりするのもこの時期で、好きな人ができたりすると、恥ずかしくて親には言えない、なんてこともよくある話。
ヘタすりゃそのまま反抗期に突入して、急に口を聞いてくれなくなったり、態度が変わったりする。
今まで普通だと思ってたのに突然?
なんてこともあるけど、それはそもそもの親子関係がうまくいってなかったことの証。
残念だけどそれはもう受け入れるしかない。
「今までのこどもに対する接し方が間違っていたんだ」
と、反省するべきところ。
ホントに関係性ができていればいろんな変化が起きた時に、まず相談されるハズ。
どんな些細なことでも。
それが理想。
そうなるためには、思春期に入るまでにどれだけの関係性を築けるか、にかかってくる。
ちゃんと我が子をみれてるか。
寄り添えてるか。
上から理不尽に押さえつけて支配しようとしてないか。
たぶんほとんどの人ができてない。
思春期に入ってしまったら…
僕の長男は現在高校生。
小学校4年生あたりから思春期に入り出したなーというのを感じた。
それまではわりと無邪気に僕に寄ってきてたのが急になくなって、言動とか振る舞いもすごく変わってきて、「男性」になろうとしてるのを感じた。
これはヘタに刺激したらマズイなと思い、僕から話しかけることは極力しないようにして、一定の距離を置いて見守ることにした。
近づくとしても、ひと言ふた言の業務連絡程度。
それ以外はほぼ話はしない。
距離を置くといっても、向こうから話しかけてきた時はちゃんと真剣に話をする。
そして茶化さない。
これは個人個人差があるけど、僕の長男の場合は冗談があまり通じるタイプではなかったので、茶化すようなことをするともうアウト、そこから一気に反抗期に入ってしまうだろうな、と判断したうえでのこと。
こればっかりはホントに個人差があるので、一概にどうこう言えることじゃない。
極論シンプルで、我が子をひとりの「人間」として向き合えば大丈夫。
てゆーか。
自分自身がどうだったかを振り返って「これはイヤだった」と思ったことは絶対にしちゃいけない。
僕の場合はそれが強かったからそうした。
その上で、ちゃんと我が子を細かいところまで観察して理解しようと寄り添えば、答えはみえてくる。
僕自身は長男が小さい頃からわりとちゃんと準備してきたので、思春期に入っても特に戸惑いを感じたり、扱いが難しいと感じたことは一度もない。
それは小さい頃からの積み重ねもあるので、一朝一夕でできるものでもないけど、だからといって、じゃあ思春期に入ってしまったらもう間に合わないのか?というとそうでもない。
僕は虎吉でこどもたちからいろんな話を聞く。
思春期真っ盛りの小学生5年生〜中学生2年生がたくさんいろんな話をしてくれる。
でも僕は彼らと幼少期からずっと過ごしてきたわけでもないし、なんなら出会ってからまだ1年にも満たない。
それでも身体の変化や精神的な変化はおろか、恋愛の話っていうかなり踏み込んだ話までしてくれる。
それってとても勇気がいることで、ましてこんなおっさんにできる話じゃない。
積み重ねてきたものなんかひとつもないのになぜ???
彼らが思春期真っ只中にもかかわらず、親と同世代の僕にそこまで開けっぴろげに話をしてくれるのは、僕が彼らをひとりの「人間」として向き合ってるから。
彼らを「こども」扱いせずに、ひとりの「大人」として接してるから。
もちろんこれはただの憶測の話で、彼らに確認をとったわけじゃない。
確認をとるなんて行為は野暮にもほどがあるし、そんなダサいことは死んでもしたくない。
思春期の彼らにいちばんやっちゃいけないのは「こども」扱いすること。
大人になるための準備期間で、なおかつ身体と精神が著しく変化してる最中にこども扱いをするのは、彼らにとっては侮辱されてるのと同義。
今まさにやろうとしてることを先に言われてしまうと、一気にやる気を失ってしまうアレと似てるかもしれない。
アレをやられた側はどうしようもなく残念な気持ちになるし、言った側の人間を軽蔑したくなる。
具体的に何をすればいいのか?
「親」という漢字
思春期のための準備を何もせず思春期を迎えてしまったら。
その場合は距離を置くのがよろしいかと。
絶妙な距離感で。
ヘタに話しかけてもヤブヘビにしかならないので、距離を置く以外に方法が思いつかない。
どれぐらいの距離感かは人それぞれで、特にこれといった決まり事みたいなものはない。
人はそれぞれ考え方も違うし、感覚も違う。
親子であってもしょせんは脳みそが違うからただの「他人」。
何を考えてるかなんてわからない。
だからこそ支配下に置いときたいっていう気持ちが生まれてしまう人もいる。
「親」という漢字は「木」の上に「立」って「見」ると書く。
大昔からそんな言葉がある。
木の上ってことは、ある程度の距離を保ちながら、でも何かあったらいつでも対応できるような絶妙な場所。
しかも木の上だったら、ぱっと見た時に姿が見えないっていう効果もある。
構いすぎず、でも何かあったらいつでも応えれるように。
そんな絶妙な距離感で黙ってみるのがいちばんイイ。
何か問題が起きたとしても、向こうから助けを求めてくるまでは絶対に手も口も出さずに温かく見守る。
そして細かいところまでよく観察することが大切。
それが「見守る」ということ。
僕自身にとってそれはなんでもなくできることだけど、いろんな人と話をしてるとそうでもないみたいで、とても難しいことみたい。
カンタンよ?
まとめ
思春期に限らず、こどもはひとりの「人間」の未成熟バージョン。
経験値も浅ければ知識も浅い。
でも、だからこそ親の人間としての真価が問われる。
親だからといって上から目線で支配しようとして、一時は恐怖で従順になるかもしれないけど、いつかどこかで必ず反発するから結局何の意味もない。
世の中の親たちはほとんどそんな考えを持ってる。
こどもは知識とか経験を親から吸収するけど、親は親でこどもから吸収することはたくさんある。
お互いにWinWinの関係性のはずなのに、親がこどもに一方的に与えてるような錯覚に陥って支配しようとすると関係性がおかしくなる。
そもそも関係性がおかしい上にこどもが思春期に突入して精神的にも不安定になると余計に拗れる。
それが反抗期。
⇒反抗期対処法・反抗期は親が作ってることにあまり気づいてない事実
思春期=反抗期
みたいな構図が当たり前になってるけど、それはこどもを支配しようとする大人が多かったからそれが一般論として言われるようになっただけ。
こどもにだって意志はあるからそれを尊重して素敵な関係を作っていけたら思春期も素敵な時間になるんじゃないかしら。
ご清聴ありがとうございました。


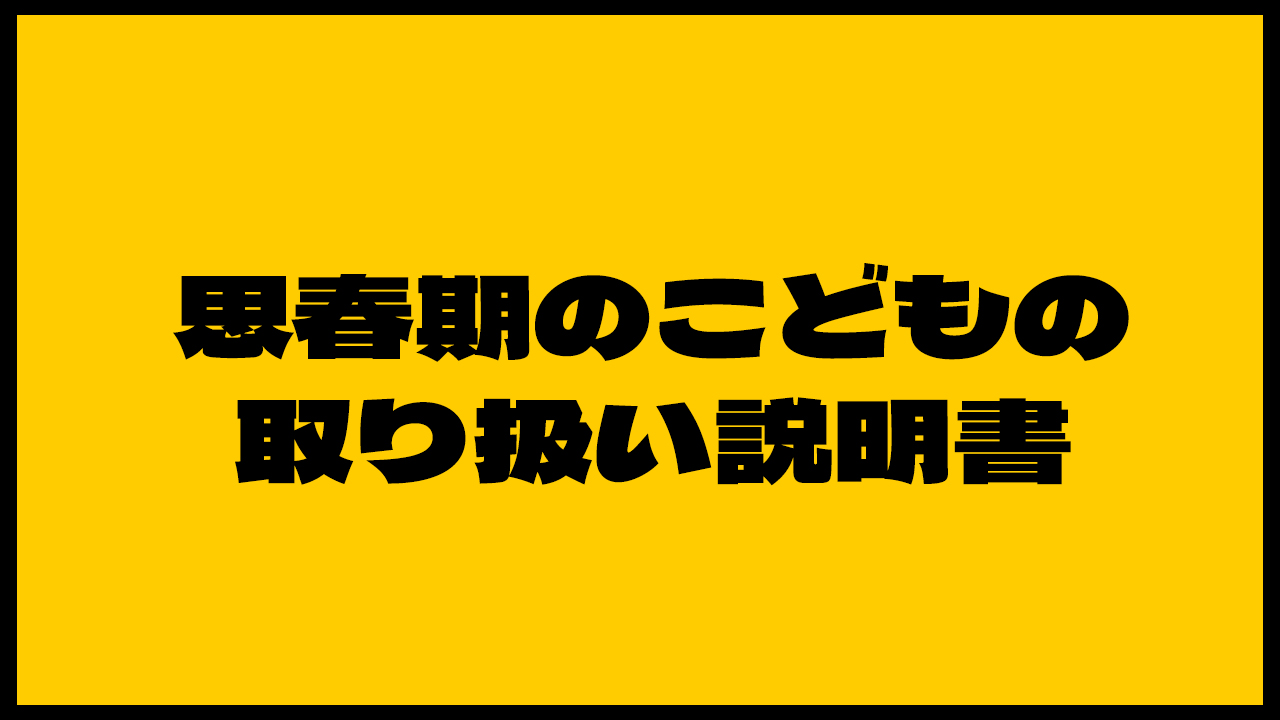


コメント