おはようございます。
こども食堂【虎吉】店主・高木のひとりごとです。
本日のテーマは『こども食堂の過去・現在・未来』。
こども食堂を運営してずいぶん時間が経って、こども食堂って一体何なんだろう?って何百回も考えた。
思ってたのとだいぶ違ったし、なんだかんだ批判の声もたくさん聞いた。
社会貢献してるはずなんだけどなぁ…。笑
その反面、嬉しいこともたくさんあった。
そんなこども食堂の過去・現在・未来。
こども食堂の歴史(過去)
「こども食堂」の歴史はまだまだ浅くて初めてその名前が出たのは、2010年ぐらいあたりからテレビとかで取り上げられるようになってから。
たぶん似たような形態はずっと昔からいろんなところであったんだろうけど、そうやって公に「こども食堂」というワードを使ったのはわりと最近の話。
こどもやその保護者、地域の住民に対して無料や安価で食事を提供する場所として認知されてるけど、対象は食べたくても食べれない、いわゆる「貧困層」のイメージが強い。
てゆーかそうやってメディアが取り上げたからそんなイメージがついてしまったんだろうけど。
そう考えるとテレビの影響力ってやっぱりすごいのねー。
…いや、昔はすごかった。
テレビって面白かったもの。
家族全員で食い入るように「カトちゃんケンちゃんごきげんテレビ」をみてたのが懐かしい。
それが今はどうだ。
コンプライアンスがウンタラカンタラでクソしょーもない番組ばかりで、地上波をみることがなくなってしまった。
そうなるギリギリ前に「こども食堂」が取り上げられて、国民の皆さまにも少しずつ認知されていった。
現代の「食」事情
「こども食堂は主に「貧困層」に対して食事を無料で提供する。」
そんなイメージを僕も持っていた。
でも実際にそんな貧困に苦しむ子が来たことはない。
仮に来てたとしてもそれを実際に耳にしたことがなく、その事実を知らない。
僕は大きな見落としをしていたことに気づいた。
実際に貧困に苦しむこどもが果たしてそれを明言するだろうか?ってことをまったく考えていなかった。
まだまだ未成熟とはいえ、幼稚園やら保育園やら小学校やら、ある程度の人間社会は経験してきている。
まわりの人との調和を考えないはずがないよなぁ、と。
だとすれば、自分の家が貧困であることを知られたくない、って考えるのが自然なんじゃないか?
そういう思考にまでなかなかたどり着けなかった。
貧困であることを明言すればイジメの的になる危険だってある。
もし来てたとしてもそんなこと口にはできないよねー。
しかも今はわざわざこども食堂に出向かなくても、自宅に食材が届くサービスだってある。
こども食堂「虎吉」にやってくるこどもたちは「美味しい」から食べに来る。
家にごはんが用意してあって、それでも食べにくるんだもの。
夕方に虎吉で食べて家に帰ってまた食べる。
そんな子がたくさんいる。
「お母さんごはんよりも美味しい」とこどもたちの口から何回も聞いた。
それはすっげぇ複雑な気持ちにはなるけど、作ってる身としては素直に嬉しい。
そんなことも鑑みるとやっぱりこども食堂って「食」のためにあるものではないよなぁ、と。
人とのふれあいの場所?(現在)
個人的な憶測だけど、食事情よりもむしろ人と人との距離が遠くなってしまったことがこども食堂にスポットライトが当たる要因になったのではないか、と思う。
困った人を助けたいって思うのは人間として当たり前の感情。
それが知らない人同士であろうが、「ちょっと作りすぎたから」と言ってご近所さんにおすそわけ、みたいな。
こども食堂という名前はなかったにしろ、そういう文化はどこにでもあったはず。
でも時代とともに人と人との距離が遠のいて、人情もクソもなくなってしまって、そういうのが珍しくなってしまった。
だからテレビで取り上げる「事態」にまで発展した。
そんな感じじゃないのかなーと調べてみたところ、全国的各地にこども食堂はたくさんあるけど、皆さんこぞって「人と人とのふれあいが希薄になった現代ーー。地域の方々とのふれあいの場所を…」みたいなことを謳ってる。
でも全国的にこども食堂は広がってるけど、頻度が少ないところがほとんど。
平均的に月に1、2回。
多くても週1回開催する程度。
その頻度でふれあいを、ってのはちょっと厳しい気がする。
しかも時間も2時間とか3時間とかに限られてるし。
はじめましてでそんな短い時間ふれあったところで、よそよそしくて気まずい空気になるのは目に見えてる。そもそも大人とこどもでは話が合わないし。
虎吉は毎日朝から晩までやってるから、いつでも来たい時に来れるし5時間いようが10時間いようがOK。
居酒屋も併設してるので、酔っぱらったおっちゃんとこどもがワチャワチャしてるのは珍しくない光景。
人間対人間なので、理解を深めるためにはある程度の時間は必要。
時間なんて関係なく深くつきあえることもある。
でもそれは自分自身のことをよくわかってる者同士で、なおかつ波長が合わないと成立するもんじゃない。
まして相手は未成熟で経験も知識も拙い人間が相手だ。
ある程度時間がかかる。
むしろこどもの方が警戒心は強くて、なかなか心を開かないし、大人のことを細かいところまでよくみてらっしゃる。
小学校の先生とかでも仕事として毎日毎日こどもたちとふれあってるにもかかわらず、関係性ができてる人はごくわずか。
現代人は人の心になかなか踏み込めないのが現実みたい。
虎吉では昭和の駄菓子屋のような雰囲気があって、こどもたちが自由奔放に振る舞える場所になっている。
あえてそうしてるにもかかわらず、SNSのコメント欄ではアホな大人が「生意気」だの、「常識ないのか」だの、程度の低いコメントを残してくださってる。
あえてそうしてることぐらいわからんかね。
そういう大人がギャーギャー騒ぎ立てるから、静かに過ごしたい頭のいい人たちが過ごしにくくなる。
そしてそういうアホの意見が当たり前みたいになって、どんどん規制がかかっていってつまらん世の中になってしまう。
テレビなんかはまさにそれで、上岡龍太郎氏が30年前に言ってたとおりの事態になってしまってる。
すげー人だ。
「こども」の表記
こども食堂は「子ども食堂」とか「子供食堂」とかいろんな表記をするけど、虎吉はずっと「こども食堂」で一貫してる。
なんか一時期、「子供っていう字の「供」が野蛮だ」みたいなことを耳にしたことがあって、あぁ…これからどんどんそういうめんどくさい世の中になっていくんだろうなぁ…と思った。
それならもう「こども」で一貫すればめんどくさいことに巻き込まれないで済むし、小さいこどもでもわかりやすい。
おぉ…これは名案だ。。。
そう考えてこうして文章を書く時とかはあえて全部ひらがな表記にしてる。
こども食堂の未来展望
これからの時代、自由に発言できる場所がどんどん減ってくる気がしてならない。
虎吉に来てるこどもたちの中には親が変にビビって、すごく不自然な言葉遣いになってしまってる子もいる。
こどもにそんな言葉を使わすのか…と。
⇒こどもが無邪気になれない現実をみた:こども食堂店主のひとりごと
#ザックリ解説すると9歳のお子さまが「またお願いします」って言い放ってそれがすっげぇ不自然だった話。
逆にそれした方が頭おかしいんちゃう?って思われることぐらいわからないのかしら?
そんなこどももいるぐらいなので、もっとおかしくなっていくのかもしれない。
だからこそこういう場所は必要なんだと思う。
事実、家出した少年の駆け込み寺みたいなこともしてるし、本気で音楽に取り組んでる子プロデュースしたりもしてる。
いろんな意見をいただくけど、自分の考えを曲げたくはないから、なんとしてでも貫きたい所存でござる。
時代は巡りめぐると信じて。
ご清聴ありがとうございました。


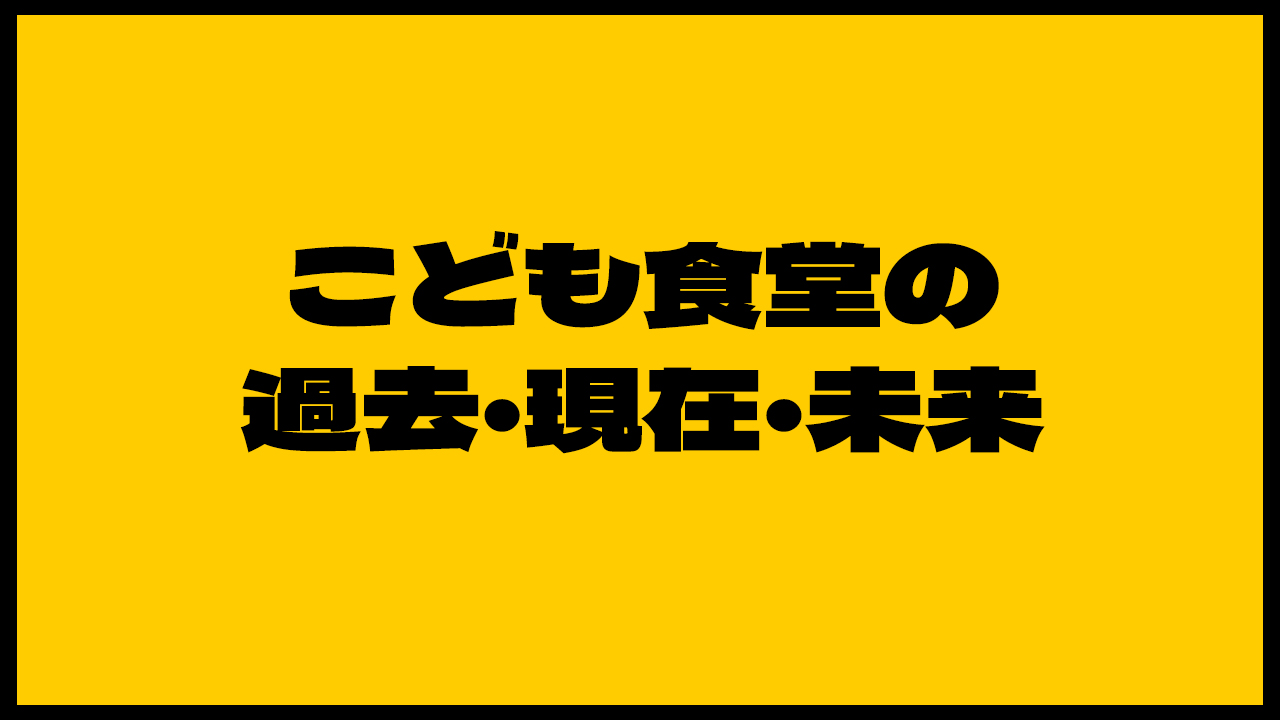


コメント