おはようございます。
こども食堂【虎吉】店主・高木のひとりごとです。
本日のテーマは『リズム感を鍛える方法』。
音楽のマニアックなお話。
リズム感は音楽だけじゃなくて日常生活においても役に立ったりする。どこでってなるとちょっと出てこないけれども。なんか洗濯物干す時とか(テキトー)。
カラオケの点数のやつは音程が合ってなくても、リズムが合ってればわりと高得点を稼げたりするので、盛り上がり度は増すかも。
音楽をやる人にとっては死活問題で、リズム感がない人はどのタイミングで音を出せばいいかが分からなくなって、超絶恥ずかしい思いをするので目ん玉かっぽじってみるがよい。
リズムは周期的に繰り返される運動のこと。
なので音楽だけじゃなくて、生活リズム、生体リズムも同じくリズムの一種。
リズム(RHYTHM)の語源はギリシャ語のリュトモス(RHYTHMOS)。
音楽のリズムを構成する要素はパルス(拍節)、拍子、ビート(拍)の3つ。
ビート(拍)が基本の単位になって、それが3つ集まったものを3拍子、4つ集まれば4拍子になる。
この世のほとんどの音楽は4分の4拍子か4分の3拍子で構成されてる。
曲によって拍が5つとか6つとか集まったもので区切ったりするのを拍節と呼ぶ。
リズム感はリズムを感じる能力のこと。
基本的に音楽は4分の4拍子で構成されてて、「1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4…..」を繰り返したものに合わせていろんな音を鳴らしたもの。
リズム感がないと、その「1.2.3.4…」をどのタイミングで打てばいいかがわからなくなってすっげー気持ち悪い音に聴こえたり、他の演奏者と合わなくて白い目でみられたりする。
幸いなことに、リズム感は生まれつきの才能とかそんな絶望的なものじゃなく、練習すればなんとでもなるもの。
ゆえにリズム感がない人はただの練習不足。
鍛えればいい。
あともうひとつ要因があるとすれば、リズムというものを根本から理解してない知識不足。
リズムは周期的に繰り返されるもので、わかりやすいのがメトロノーム。
↑これはBPM(テンポ)120。
音だけで聴くとイメージがしにくいから分かりにくいので。
こうして時計が回り続けるようなイメージを持つとリズムを視覚的に理解できる。
↑こんな感じで行ったり来たりするようなイメージを持つこともある。
これはこれで素晴らしいんだけど、厳密なことを言うと切り返しの時に、わずかに止まる瞬間があったりするので個人的には好きじゃない。
音楽は曲が始まってから終わるまで、途切れることなくリズムは常に動いてる。
円でイメージすれば途切れることはないので、ちょうどいい。
♾のマークも途切れることはないけど、これだと3拍子とか奇数の拍子の時にややこしくなるので円がたぶんいちばんイイ。
回り続けるものは円なの。
それこそ時計とかタイヤとか、観覧車とか。
円のイメージを持つと拍と拍がつながってまわり続ける。
円は1拍で4分音符なので、円の半分の青いところで音を出せば8分音符になる。
さらに細かく緑のところで音を出せば16分音符になる。
この円のイメージを持って曲を聴くと、リズム感が鍛えられる。
そしてこの円は映像だと、体の面に対して平行に円を描くようなイメージになってる。
でも実際は、体の面に対して垂直に円を描くようなイメージを持つとリズムは安定しやすい。
プロのミュージシャン、特にベーシストの方のリズムのとり方をみてみるとそういうリズムのとり方をしてる人は多い。
あとDJやってる人とかもそう。
横じゃなくて縦。
なんかハトとかニワトリみたいな動きになる。
たぶんこれは横でリズムをとるよりも縦でリズムをとった方が演奏しやすいんじゃないかなーと。
とりあえず。
この円のイメージを持つことがリズム感を鍛える第一歩。
こういうイメージを持った上で、細かくリズムを刻む練習をする。
好きな曲を聴きながら自分の中で細かいリズムを鳴らして、円を描くイメージを持つ。
これは歩きながらでもできるし、ボーッとしてる時でもできるし、ちょっとしたスキマ時間とかに場所を問わずいつでもできる。
細かいリズムは指を動かしてヒザを叩いたりして実際に音を鳴らすと、自分で出した音を確認できるので、なおリズム感は鍛えられる。
大事なのは細かい音と音の間もつながってるっていうイメージを持つこと。
音と音の間にもリズムはあって、その空間を自在に操ることができるかどうかがグルーヴを生み出せるかどうかにつながってくる。
がんばってー。
ご清聴ありがとうございました。


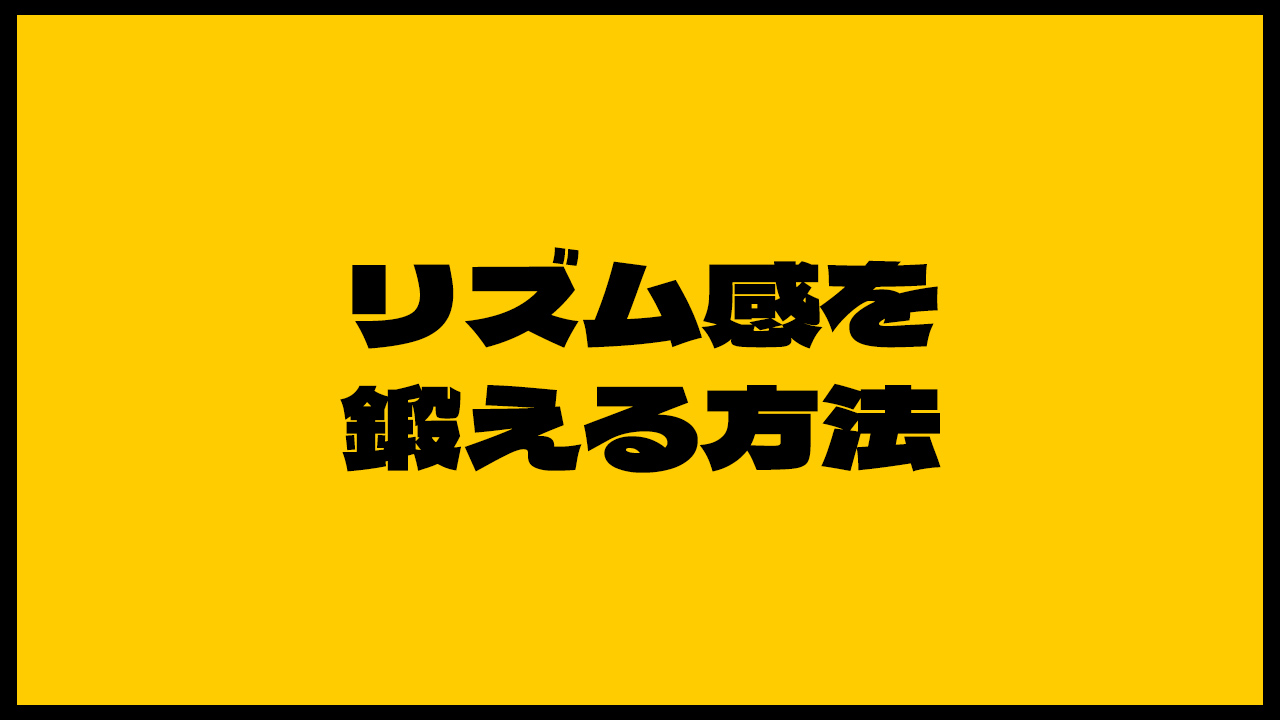


コメント